2019.01.31
法医学女子のDNA鑑定教室 -ほぼ他人!「またいとこ」までわかるDNA鑑定の方法...
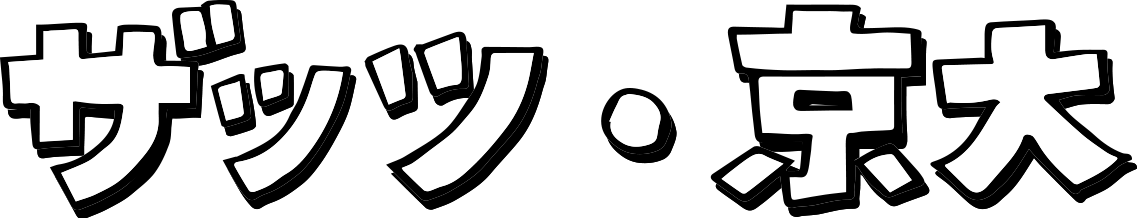
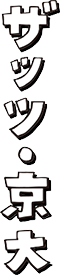
ザッツ編集部のもとに、またまた耳寄りな情報が寄せられてきました。
「実は、漢方の原料になる植物やハーブ類などが植生している「薬用植物園」があるらしいですよ。そこなら、広報Bさんの冷え切った体と心を救ってくれるヒントがあるかもしれません!!!」
冷え切った心ってのはよくわかりませんけども、とにかく「薬用植物園」ってものがあるらしい。
これは、潜入するしかない!

そもそも「薬用植物園」って、どんな植物園?

京都大学の「薬用植物園」は、薬学研究科・薬学部の研究用施設として1968年に設置されました。3,042㎡の面積を有しており、標本園、温室、栽培圃場、樹木園などから構成されています。
園内では、日本薬局方に収載される漢方薬原料植物などの重要薬用植物のほか、海外学術調査などで収集した貴重な薬用植物を栽培・管理し、学生の教育のみならず創薬科学の研究のために増殖・利用を図っています。
1980年代からは、圃場を利用してシソ・エゴマに関する遺伝・育種学、遺伝生化学、系統分類学的研究が行われてきました。これらによって固定・育種された系統のほか、国内外の調査研究で収集された系統もあり、現在ではシソの保有系統数は5,800を超え、国内最大規模のコレクションとなっています。また、中近東、中央アジア、東南アジアなどにおける海外学術調査で収集した、薬用植物のさく葉標本はおよそ5,000点、生薬標本は1,100点あり、研究・教育に活用されています。(※さく葉標本は、移転に伴いすべて京都大学総合博物館に移管しました。園内には、授業で使用する生薬標本のみが残っています。)
ここでご注意!
「薬用植物園」は、一般の方の立ち入りは禁止です。ご了承いただきますようお願いします。
ふつうの植物園とは違う、京大薬学研究科ならではの
「薬用植物園」を案内してもらいました!
今回、園内を案内してくれたのは、伊藤 美千穂 薬学研究科准教授。
生薬に関する研究をして20余年、園内の植物たちの生息状況を知り尽くし、まるで我が子のように日々のメンテナンスをするまさに薬用植物園マスターです。
 ひっそりと位置する植物園入口。白衣の学生さんがいるところも、大学の植物園ならではの風景。
ひっそりと位置する植物園入口。白衣の学生さんがいるところも、大学の植物園ならではの風景。 薬用植物園マスターこと伊藤先生。園内の植物のことなら何でもござれ! 案内する様子から、植物たちへの愛情がヒシヒシと伝わってきます。
薬用植物園マスターこと伊藤先生。園内の植物のことなら何でもござれ! 案内する様子から、植物たちへの愛情がヒシヒシと伝わってきます。「薬用植物園マスター」伊藤先生による、園内ツアースタート!
取材時は11月という季節柄、既に枯れてしまっているものも多かったのですが、春になると、さまざまな植物が花を咲かせてとても賑わうそうです。
貴重な研究材料である園内の植物たちを一挙に紹介します!
(植物図鑑なみにいろんな植物を紹介していきます!)
 のどに良いことで有名な「カリン」。今年は豊作だそうですよ。
のどに良いことで有名な「カリン」。今年は豊作だそうですよ。 近づくと、とってもいいにおい! 広報Bもお土産にいただきました! いただいたカリンは、はちみつ漬にしてみましたよ。
近づくと、とってもいいにおい! 広報Bもお土産にいただきました! いただいたカリンは、はちみつ漬にしてみましたよ。 ビタミン豊富で、胃によいとされる「サンザシ」。まさに収穫時期です。
ビタミン豊富で、胃によいとされる「サンザシ」。まさに収穫時期です。 こちらは「オウバク」。樹皮を剥ぎ取り、乾燥させて用います。ベルベリンをはじめとする薬用成分が含まれ、強い抗菌作用を持つため、主に健胃整腸剤として用いられます。
こちらは「オウバク」。樹皮を剥ぎ取り、乾燥させて用います。ベルベリンをはじめとする薬用成分が含まれ、強い抗菌作用を持つため、主に健胃整腸剤として用いられます。 ん? この袋はなに・・・? これは、「シソ」の実。研究に使用する「遺伝的に純系」な種をとるために、自然交配しないように袋づけをするんですって。
ん? この袋はなに・・・? これは、「シソ」の実。研究に使用する「遺伝的に純系」な種をとるために、自然交配しないように袋づけをするんですって。 「シソ」の花。春先には、こんなキレイな花が咲きます。
「シソ」の花。春先には、こんなキレイな花が咲きます。 こちらは「クチナシ」。利尿作用、胆汁の流れを良くする作用があります。お正月の栗きんとんの色つけに使われるのもコレなんですよ。
こちらは「クチナシ」。利尿作用、胆汁の流れを良くする作用があります。お正月の栗きんとんの色つけに使われるのもコレなんですよ。 かわいらしい朱い実は「サンシュユ」。滋養強壮に良いのだそう。
かわいらしい朱い実は「サンシュユ」。滋養強壮に良いのだそう。 根茎の部分が使われる「ホソバオケラ」。殺菌作用があるので、煎じて飲んだり、くすべて煙を出したりして使います。独特のにおい。八坂神社(京都)の元旦の神事「をけら祭」のおけら火にはこれが使われるそう。
根茎の部分が使われる「ホソバオケラ」。殺菌作用があるので、煎じて飲んだり、くすべて煙を出したりして使います。独特のにおい。八坂神社(京都)の元旦の神事「をけら祭」のおけら火にはこれが使われるそう。 何とも不思議な、細く垂れ下がっている実は「キササゲ」。利尿作用があり、腎臓病に効くとされています。
何とも不思議な、細く垂れ下がっている実は「キササゲ」。利尿作用があり、腎臓病に効くとされています。 キササゲの細いさやの中には、こんな小さな、わたげのような種子が詰まっています。
キササゲの細いさやの中には、こんな小さな、わたげのような種子が詰まっています。
 「マリアアザミ」。名前に反して、葉は鋭いトゲに覆われています。これがかなり痛い!肝臓疾患に効くため、お酒呑みの強い味方。
「マリアアザミ」。名前に反して、葉は鋭いトゲに覆われています。これがかなり痛い!肝臓疾患に効くため、お酒呑みの強い味方。 珍しい「シロバナタンポポ」。日本で見られるタンポポのほとんどが西洋タンポポになってしまっている今、とても貴重な在来種なんです。
珍しい「シロバナタンポポ」。日本で見られるタンポポのほとんどが西洋タンポポになってしまっている今、とても貴重な在来種なんです。 ハーブで有名な「レモンバーベナ」。葉っぱをこすると、爽やかないいにおい!
ハーブで有名な「レモンバーベナ」。葉っぱをこすると、爽やかないいにおい! 「ジギタリス」。むくみの解消に良いそうで、本国イギリスではメジャーな生薬だそう。
「ジギタリス」。むくみの解消に良いそうで、本国イギリスではメジャーな生薬だそう。 ジギタリスの花。春にはこんな個性的な花を咲かせます!
ジギタリスの花。春にはこんな個性的な花を咲かせます! 「ボウコウナン」。煎じて飲むと健胃や利尿効果があるとされます。
「ボウコウナン」。煎じて飲むと健胃や利尿効果があるとされます。 さやの中に種子が詰まった「ケツメイシ」。利尿作用、便秘解消に良いそう。
さやの中に種子が詰まった「ケツメイシ」。利尿作用、便秘解消に良いそう。 ケツメイシの種子。まるで粒チョコみたい。煮出してお茶にするのが一般的。
ケツメイシの種子。まるで粒チョコみたい。煮出してお茶にするのが一般的。 不思議なフォルムの「ゲンノショウコ」。その形から、「みこし草」とも呼ばれます。胃薬や下痢止めとして。
不思議なフォルムの「ゲンノショウコ」。その形から、「みこし草」とも呼ばれます。胃薬や下痢止めとして。 小さい花がかわいらしい「エンメイソウ」。「ジテルペン配糖体」が含まれています。「葉っぱをかじってみて」という先生に言われるがままかじると・・・苦い~! 配糖体が入ってるのに、苦いんですね・・・。
小さい花がかわいらしい「エンメイソウ」。「ジテルペン配糖体」が含まれています。「葉っぱをかじってみて」という先生に言われるがままかじると・・・苦い~! 配糖体が入ってるのに、苦いんですね・・・。 エンメイソウの不意打ちの苦みに、まさに苦い顔をしていると、「今度はこれ、かじってみて」と先生。恐る恐るかじると・・・甘~い!こちらは甘味料でも有名な「ステビア」。ステビアにも「ジテルペン配糖体」が含まれているそう。苦みと甘み、植物によって表れ方が違うなんて、何とも不思議です。
エンメイソウの不意打ちの苦みに、まさに苦い顔をしていると、「今度はこれ、かじってみて」と先生。恐る恐るかじると・・・甘~い!こちらは甘味料でも有名な「ステビア」。ステビアにも「ジテルペン配糖体」が含まれているそう。苦みと甘み、植物によって表れ方が違うなんて、何とも不思議です。 「ジオウ」。生のままを「鮮地黄」、そのまま乾燥させたものを「乾地黄」、蒸してから乾燥したものを「熟地黄」というそう。血を補って滋養する効果で知られている生薬です。
「ジオウ」。生のままを「鮮地黄」、そのまま乾燥させたものを「乾地黄」、蒸してから乾燥したものを「熟地黄」というそう。血を補って滋養する効果で知られている生薬です。 有名な「ドクダミ」。先ほど出てきた「ゲンノショウコ」のほか、「センブリ」と合わせて、「日本3大和薬」とされています。
有名な「ドクダミ」。先ほど出てきた「ゲンノショウコ」のほか、「センブリ」と合わせて、「日本3大和薬」とされています。 かわいらしいドクダミの花。開花期の地上部を乾燥させたものは、「十薬」または「重薬」と呼ばれ、十の効能を持つ重要な薬といわれています。煎じてお茶にするのが一般的。
かわいらしいドクダミの花。開花期の地上部を乾燥させたものは、「十薬」または「重薬」と呼ばれ、十の効能を持つ重要な薬といわれています。煎じてお茶にするのが一般的。 ご存知「ラベンダー」。実は、いい香りなのは花の部分だけ。葉っぱはくさいんです・・・。
ご存知「ラベンダー」。実は、いい香りなのは花の部分だけ。葉っぱはくさいんです・・・。
こちらはすべて「ミント」。一番左の「ハッカ」が最もメントールが多く、「生薬の気剤」とされています。4種類、全てニオイが違うのにビックリ!!! 一番右のミントが最もメジャーで、先生曰く「レアチーズケーキにのってるやつ!」とのこと(笑)。
 「パイナップルセイジ」。名前のとおり、なんと葉がパイナップルの甘いにおい。
「パイナップルセイジ」。名前のとおり、なんと葉がパイナップルの甘いにおい。 お茶にすることでご存知の「ハトムギ」。種子を乾燥させて用います。
お茶にすることでご存知の「ハトムギ」。種子を乾燥させて用います。
園内の中心に位置するハウス。温室内では、「沈香」や「桂皮」のほか、熱帯性の薬用植物などが植えられています。
 ハウスの中は、常に最低温度10度を下回らないようにキープ。熱帯、亜熱帯地方や東南アジア地域をはじめとするさまざまな植物が生息しています。
ハウスの中は、常に最低温度10度を下回らないようにキープ。熱帯、亜熱帯地方や東南アジア地域をはじめとするさまざまな植物が生息しています。 香道で用いられる香木として有名な「沈香」。ここには、中国産やベトナム産が栽培されています。
香道で用いられる香木として有名な「沈香」。ここには、中国産やベトナム産が栽培されています。 こちらは「桂皮」。ケイ(桂)やニッケイ(肉桂)の樹皮で、一部地域で産出する肉桂がスパイスのシナモンと呼ばれているもの。
こちらは「桂皮」。ケイ(桂)やニッケイ(肉桂)の樹皮で、一部地域で産出する肉桂がスパイスのシナモンと呼ばれているもの。今回の案内人、伊藤先生にお話を聞きました
Q.大学の研究施設としての「薬用植物園」の特徴と意義とは?
一般の植物園とこの薬用植物園の違いは、何よりも、研究のための植物園であるということ。
研究対象を、サンプルとしてだけでなく、生きた植物として育てることで、その全容と付き合うことができ、研究に幅ができると思います。
生薬の研究をする際でも、乾燥された生薬を市場で購入して実験に使うのと、同じ植物を植物園で育てて、収穫して、処理して実験に使うのとでは、まったく違います。育てながら、細部を見て、時間の経過とともに変わりゆく姿を観察し、世話をして反応を見る。そうすることでいろいろ考える機会が生まれるので、乾いた生薬しか知らない人とは一味違う発想ができます。そういう場を提供してくれるのが、この薬用植物園だと思います。
Q.先生ご自身はどのように「薬用植物園」を活用されていますか?
私の研究では、研究に利用する植物を園の圃場や温室で育てており、必要に応じて新鮮葉を採取して使ったり、交配実験を行ったり、学生たちの学会発表のための写真をとったり・・・とさまざまに活用していますよ。
番外編というか、広報Bの意外と女子力高い一面をご紹介
カリンのはちみつ漬けをつくってみました!
お土産にいただいたカリンで、はちみつ漬けを作ってみました。かりんは古くから咳止めやのどの痛みに効果があるとされています。また、カリンに含まれるクエン酸は、新陳代謝を活発にして冷え性の原因である血行不良をよくしてくれるそう。これは冷え性の広報Bにはもってこい!
 カリン3個あたり、1kg程度のはちみつを使います。もぎたてのカリンはいい香り。
カリン3個あたり、1kg程度のはちみつを使います。もぎたてのカリンはいい香り。 1cm程度の輪切りに。カリンの皮はとても硬いので要注意。断面図はこんな感じです。種にも薬効成分があるので、そのまま入れます。
1cm程度の輪切りに。カリンの皮はとても硬いので要注意。断面図はこんな感じです。種にも薬効成分があるので、そのまま入れます。 輪切りにしたカリンとはちみつを、熱湯消毒したビンの中に交互に入れていきます。目安はカリンがはちみつに完全にかぶるくらいです。あとは蓋をして冷暗所に置きます。1~2ヵ月たてば飲み頃。お湯で薄めていただきます。
輪切りにしたカリンとはちみつを、熱湯消毒したビンの中に交互に入れていきます。目安はカリンがはちみつに完全にかぶるくらいです。あとは蓋をして冷暗所に置きます。1~2ヵ月たてば飲み頃。お湯で薄めていただきます。「京都大学の薬用植物園」、いかがでした?たくさんの植物を紹介してみました。
園内の薬用植物の数々は、研究材料として単に利用されるだけではないんです。実際に、植物たちの成育を手がけ、日々の息づかいにていねいに耳を傾けることで見えてくること、気づくことが、新たな研究の糸口へとつながる大きな可能性があります。
日々の努力ですよね、こういう日々の地道な研究を突けられている先生が京大にはたくさんいるんですよね。ザッツ京大ですね。
そんな薬用植物園は、まさに薬学研究のフィールドワークの場。ここから生まれる新たな研究成果が、いつかたくさんの人を救う種になればと思います。
冷え性を解消するヒントももらえ、広報Bも救われました!