2017.03.08
京大の先生に触れることができる!先生お気に入りのスポットをご紹介
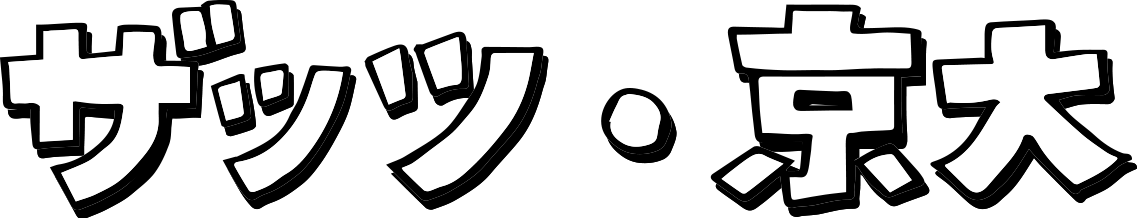

こんにちは。
『ザッツ・京大』編集部です!
はじまりの季節である4月!
新入生や新社会人など、夢に向かって新たな一歩を踏み出したという人も多いのではないでしょうか。
夢が叶うタイミングは人それぞれですが、京都大学にはとても早いタイミングで「プロ」となった学生がいます。
それが、総合人間学部4回生の青羽悠さん。
彼はなんと、現役京大生の小説家なのです!

青羽さんは2016年、高校時代に執筆した『星に願いを、そして手を。』が第29回小説すばる新人賞を受賞し、わずか16歳でデビュー。京都大学に進学し、昨年、2020年には『凪に溺れる』を発表しました。
京都大学はこれまでにも、多くの著名な小説家を輩出してきました。
最近では、万城目学氏や森見登美彦氏が大いに活躍されています。
そこに名を連ねる現役京大生作家とは、いったいどのような方なのでしょうか? 作品はもちろん、4回生を迎えた今、大学生活についても、ぜひともお話をうかがってみたい!
……ということで取材を敢行。
小説家になりたい人はもちろん、夢を追いかけている人はぜひご覧ください!
——本日は、お忙しいなか、ありがとうございます。小説のこと、大学のこと、いろいろとうかがえればと思います。早速ですが、青羽さんはいつ頃から小説を書き始められたのですか?
「そうですね。中学校を卒業した後の春休みから『星に願いを、そして手を。』を書き始めました。執筆期間はだいたい1年くらいです」

史上最年少で第29回小説すばる新人賞を受賞した青羽さん。受賞作『星に願いを、そして手を。』(青羽悠、集英社)は、宇宙に夢中だった中学時代の同級生4人組が、社会人になって再会し、自分たちの夢や身近な大人の夢に向き合っていくというストーリーです。
——初めて書いた作品で受賞&デビューされたんですか?! すごいです。書き始めたきっかけは?
「これというきっかけはないのですが、その頃『このままでいいんだろうか?』と、すごく強く思ったんです。つまり、このままなんとなく大人になっていっても、何も見えてこないんじゃないかと。今思えば気が早いんですが、中学生・高校生なりの切迫感をもっていろいろ考えたんですね。『今やらないと何も始まらない』という気持ちに駆り立てられました」
——なるほど。「切迫感」ですか。当時はどんな高校生だったんですか?
「本当に楽しい高校生活でした。いい仲間に恵まれて、成績も悪くない、たいていのことは器用にこなせる『ほどほどの優等生』。でもその器用さが嫌だったからこそ、小説を書いたというところもあるんだと思います」
——楽しくてもどこか足りないような感覚があったんですね。高校生活はなかなか忙しいと思うのですが、当時はどんな執筆スタイルだったのでしょう?
「学校から帰ってきて、勉強をすべて終わらせてから書いていました。毎晩1〜2時間、ほんとうにちょっとずつ進めていましたね」
——毎日書き続けるのって、すごく難しいことだと思います。
「自分でもよくやれたなと思います(笑)。今は小説を書くということに慣れてきて、技術も身についてきましたが、当時はまったくの未経験。でもその分、思い切ったことをできる勢いがあったんですよね。自分の将来について『何かになりたい』という強い思い・渇望に突き動かされていました」
——その衝動は一瞬ではなく、ずっと突き動かされ続ける本当に強いものだったんですね。ところで『星に願いを、そして手を。』は高校時代に書かれた作品でありながら、主要登場人物の4人が20代の社会人や大学院生なのが意外でした。どうしてその年齢層を描こうと思ったのですか?
「当時も今も、僕のなかには『ちょっと先の未来が不安』という気持ちが常にあるんです。どうなるかわからない将来への不安。その不安と折り合いをつけるために、自分の人生のちょっと先に焦点を置いて書いています。経験を書くのではなく、自分の人生の延長線上にあるものを書いているという感覚です」
——小説を書いているということは、誰かに話していましたか?
「いえ、ほとんど誰にも言いませんでしたね。親にも言っていなかったので、受賞したときにはすごくびっくりしていました(笑)。今となっては仕事になっているので小説家と名乗っていますが、当時は人に言いたくなくて」
——そうなんですか?! ちなみに、言いたくなかったのはなぜでしょうか?
「自分のことを『イタいやつ』だと思っていました。受賞というある種の保証をされたから表に出ることができましたが、それがなければ自意識過剰と思われそうなのが嫌だったんです。でも『書きたい』というのは事実だったので、その折り合いには苦しみました」
——自分にとって大切なことだからこそ、人に話して傷つけられたくないという気持ちになるのかもしれませんね。ところで一口に「文学賞」といってもいろいろな賞がありますが、そのなかでも小説すばる新人賞を選んだ理由は?
「書き切るための目標として、すばる新人賞の締め切りがちょうどよかったんです。だいたい1年くらいあったので、余裕をもって書けるかなと。結果的に、自分に合った賞を選ぶことができたと思います。ただ当時は、賞を取れるなどとは到底思いませんでした。それよりも書き切ること、やりとげることを大切にしていました」
——大学生活についてもお話を聞かせてください。どうして京都大学に進学しようと思われたのでしょうか?
「そうですね、感覚として『導かれた』としか言いようがないのですが……あえて理由を探すのであれば、まず京都というフィールドが魅力的でしたね。狭くてちょっと閉鎖的で、いいものが煮詰まっているようなこの土地に来てみたかったんです。
それから『京都大学』の4文字から、モヤのように立ち上っている何か(笑)。優秀なだけじゃない、なにか芳しいものが出ているような気がしました。実際に入ってみるとおもしろいものがいっぱいあって、入学前の直感は間違っていなかったと思います」
——モヤというのは、空気感のようなものでしょうか?
「そうですね、ほかの大学とは明らかに違う空気があると感じました。大学に入って、その正体がわかった気がします」
——その正体とは……?
「いろんな価値観が存在しているということです。考えの幅の広さや自由さを、京都大学にいる全員が感じているんじゃないでしょうか。そういう自由さが地面から湧き立ち、キャンパス内に活発さが生まれている。それを、受験生も感じ取っている気がします」
——キャンパス内に自由な土壌が培われているということですね。京都大学に入学してよかったと思うのは、どういった点ですか?
「やっぱり、決まった価値観がないというのがいちばん大きいですね。京大って、ある種の野性味というか、タフさを求められる大学だと思うんですよ。好き勝手にやりたいことをやっていいけど、その分自己責任が求められる。それがすごくいいところです。しっかりいろんなことを見て、いろんな経験をして、自分の信じるものを自分でつくりなさいと言われているような。自分をゆっくりと養い育てていくプロセスをすごく大切にしているのが、この大学のタフなところだと感じます」

青羽さんのお気に入りの場所は、文学部東館の中庭。周囲から置き去りにされ、時間の流れが止まっているような特殊な空間なのだそう。学生から教授まで、多くの人が集まる場所でありながら、いつも不思議と静かです。
——青羽さんは今、どのようなことを学んでいるのでしょうか?
「地球科学のゼミに所属して、地震や気象について研究しています。もうひとつ興味をもっているのは、『複雑ネットワーク』という学問。来年は大学院に進学するつもりですが、そこではこの複雑ネットワークを中心に研究したいと思っています」
——2作目の『凪に溺れる』にも、複雑ネットワークを研究する大学生が登場していましたね。どんな学問なのでしょうか?
「簡単にいえば、ものごとのつながりを見る研究です。人・もの・お金などの切り口から、いろんなスケールで分析していって、どこが重要なのか、今後必要なのはどの部分なのかといったことを明らかにしていきます。
複雑ネットワークに惹かれるのは、『いろんなものが散らかっている』という感覚を持っているから。僕個人のことでいえば大学でいろんな学問に出会ったり、社会的に見ればビッグデータによっていろんなところから情報が取れるようになっていたり。散らばったままでまとまりのないたくさんの情報について、その結びつきを整理して、いろいろな見方で理解するということができていない気がしています。
それを感覚的にではなく学問的に行うというのが、複雑ネットワークはすごく魅力的で。これからぜひとも深く研究していきたいです」

大学3回生のときに発表した第2作『凪に溺れる』(青羽悠、PHP研究所)。同級生やバンド仲間、音楽プロデューサーなど、複数人の視点と回想が絡み合い、少しずつ夭逝した天才ミュージシャンの姿と人生が浮き彫りになっていきます。今作でも、ただ甘いだけでも、苦いだけでもない、それぞれの夢と現実のざわめきが丁寧に描かれています。
——青羽さんの小説は2作品とも群像劇で、複数の人間の視点がつながりあってひとつの大きな流れが浮き上がってくるという構成になっている気がします。執筆活動と複雑ネットワークへの関心に、つながりはあるのでしょうか?
「小説を書くときには流れを重要視しているので、そう考えてもらえるのはとてもうれしいです。ものごとがどのようにつながっていって、最後に何が見えてくるのかというのは、すごく意識しているところで。小説を書くということ自体、現実をいろいろな方向から見る作業だと思っています」
——作家として、大学生活ではどのようなことが刺激になっていますか?
「具体的に言うのはすごく難しいですね……。今の経験は、これからどんどん小説につながっていくとは思うんです。ただ、それはもっと先のこと。実は京大に入学してすぐに大学生の話も書こうとしたのですが、うまくいきませんでした。そのときの僕にとっては近すぎた世界なんだと思います。現在の生活や空気感も、少しして振り返ったとき、ようやく小説のなかにかたちとして表れてくるのではないでしょうか。
何に刺激を受けているのかはまだわからないけれど、大学生として学んだり、いろいろな人と出会ったり、飲み会に出たり、女の子に振り回されたりと(笑)、毎日いろんなことをしながら生きていくこと。それが今やるべきことだと思っています。そのなかで、自分にとって大事なもの、必要なもの、二の次でいいものという序列ができてきました。自分だけの価値観がつくりあげられつつあるという感覚はすごくあります」
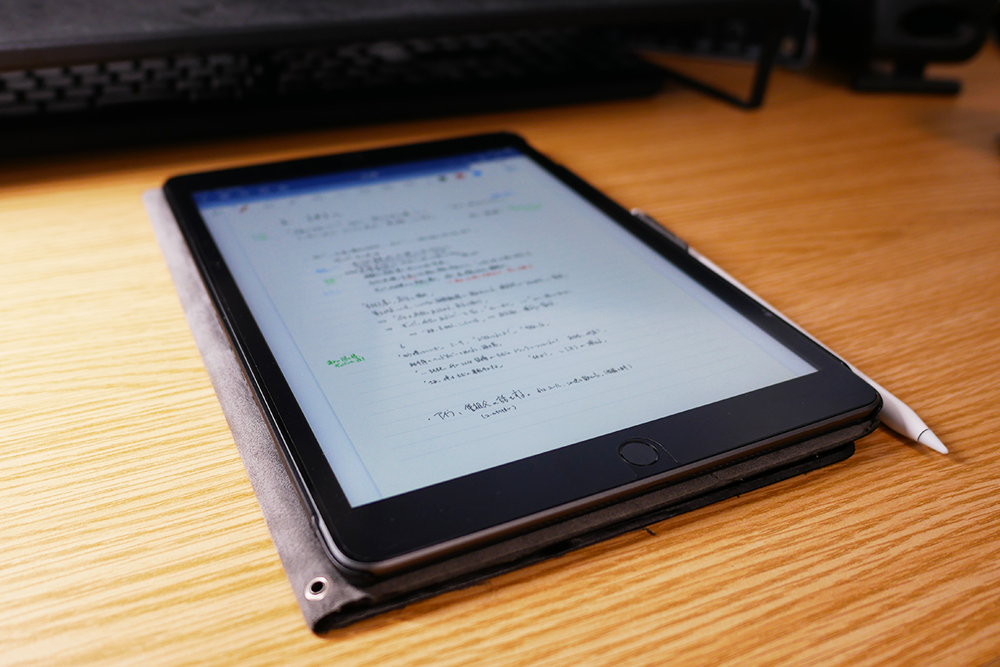
創作メモやプロットの作成はiPadで行っているという青羽さん。執筆をするのはパソコンだそうです。
——なるほど、いつか振り返ったときに初めて、何に刺激を受けたのかがわかるということですね。大学に入学して、執筆活動に変化はありましたか?
「1作目が出てすぐに受験だったので、1年間は執筆をストップしていました。大学に入ってからまた書き始めたのですが、最初の1年半くらいはうまく書けなくて。『大学生』というものに慣れてきて、高校生のときとは別のステージに来た感覚が得られた頃に、やっと次の作品を書くことができました」
——うまく書けなかったのは、何か理由があるのでしょうか?
「きっとどの大学生もそうだと思うんですが、1、2回生のときって、なんだか慌ただしくて落ち着かないんですよね。僕も京大に入ってから、考え方や価値観を大きくつくりかえてきました。小説は自分を投影するものですが、投影する母体である自分自身がどんどん変化していたので、ひとつの作品に落とし込むことができなかった。今は自分を変えるという作業が落ち着いたので、3作目・4作目もうまく書くことができると思っています」
——『星に願いを、そして手を。』も『凪に溺れる』も、夢をテーマにした作品でした。大学生活を経て、青羽さんのご自身の夢に対する思いに変化はありましたか?
「最近は将来の選択肢がどんどん狭まってきて、具体性を増して、『夢』が『職業』という言葉に置き変わってきました。そういう転換を経たので、今後の作品には夢があまり出てこなくなるかもしれません。
これから書いていきたいのは、自分の将来よりも、いろんなものごとの将来。焦点が自分を離れていって、内省的ではなく外向きの作品になっていく予感があります。これから小説を通じていろいろなものを見ていきたいし、いろいろなことが投影された作品を書いていきたいです」
——1作目は一人称でしたが、2作目は三人称で書かれていましたよね。それも焦点の変化と関係しているのでしょうか?
「そうかもしれません。最初の小説はもともと世に出る予定はなく、本当の意味で自分のためだけのものだったので。いつかまたそこに戻るのかもしれませんが、今は自分自身とようやく折り合いがついたので、外をのぞきに行ってみようという気持ちです」
——青羽さんの作品は夢を叶えることだけでなく、挫折もしっかりと描かれていますが、お話をうかがっていて「挫折」ではなく、将来における別の「選択肢」として描かれているような気がしてきました。
「そうですね。夢を叶えたとしても、挫折したとしても、人生は続いていくじゃないですか。いずれにしても、将来の可能性が絞られてしまうことへの切なさがあると思うんです。僕は『夢を叶える』という区切りがすごく早いタイミングで来て、今は『小説家』を名乗っていますが、やっぱりほかの可能性もあったんじゃないかと、ずっと心に残り続けているものがあって。それに『可能性』という言葉が『職業』という言葉に狭められていくことの寂しさも感じています。そういう可能性について、僕は小説で描かなければならないと思っています」
——次回作は、どのような小説になるのでしょうか?
「今は2つ動いていて、ひとつは現実的な話。年代などが僕に近い人たちのことを書くことになりそうです。『今の僕ら』について、時代を意識しながら真剣に考えていきたいなと。
先ほど、入学当初に『自分と近すぎる世界を描こうとしてうまくいかなかった』というお話をしましたが、最近は比較的近くも見られるようになってきた気がしています。
もうひとつはかなりチャレンジングで、すごく大きな規模の物語にしたいと思っているんです。時間的にも地理的にも限界まで規模を広げて、いろいろなものがつながって流れていくことを書きたい。物語としてどこまで視点を拡大していけるのかという挑戦をしています。
自分がいるところを見るやり方と、すごく広いところを見るやり方の2つを試しているわけですが、自分自身を含め、いろんなものを見て小説を書けるようになってきたということだと思います」

青羽さんの執筆のスイッチはコーヒー。丁寧に1杯入れてから、パソコンの前に座るとのこと。
——『凪に溺れる』では、ひたむきに夢を追いかける中学生2人が、周囲から孤立していたのが印象的でした。こうした孤独感の表現は、青羽さんご自身の経験と重なるところがあるのでしょうか?
「そうですね……僕に限らず、また小説に限らず、『自分はこういうことをやるんだ』という強い気持ちをもっていれば、ひとりでやらなければならない作業っていうのは必ず出てくると思います。そういうところが、小説にも表れているんでしょうね。
僕が最初の作品を書いたときは、外から与えられる評価に対して努力をするというよりも、『自分でここまでやる』という自己完結的な満足を求めていました。自分で書いてよかったと思えるものが書きたかった。だから、評価されること自体はうれしかったのですが、感想をもらってもどうしていいかわからなくて。僕のなかではひとりで書き上げた時点で、『小説』という営みが終わっているのかもしれません」
——なるほど。自分のために何かを成し遂げようとするときに、孤独というものは必要不可欠なのかもしれませんね。最後に、今、夢を追いかけている人に向けてメッセージをお願いします。
「小説の話になってしまうのですが……編集者の方から聞いた、すごく印象的な話があって。新人賞に応募されてくる作品の文章って、昔よりもきれいに読みやすくなっているそうなんです。『活字離れ』とよくいわれますが、SNSの普及などを通して文章に接する機会自体は増えていて、日本語のうまい人が増えているのかもしれません。でもその一方で、『真に迫るもの』がなく、あらすじだけで事足りてしまうような小説がすごく多くなっているらしいんですね。
その話を聞いたとき、僕がやらなきゃいけないのは『メッセージ』だと思いました。小説を書く理由はいろいろあって、それは僕のようにメッセージだったり、『こういうものを見せたい』というイメージだったりしますが、結局はそういうものに向き合っていくしかない。僕は運がいいことに、雑念なくそれができました。文章やストーリーの流れというのは、テクニックでしかありません。それよりも自分と向き合って、本当にやりたいことを見つめるのが大切だと思いますし、それは小説に限らないと思います」
——青羽さん、ありがとうございました!
