2019.01.17
芋を洗うサル。ほんとにいるの?? 確かめに行ってきました!
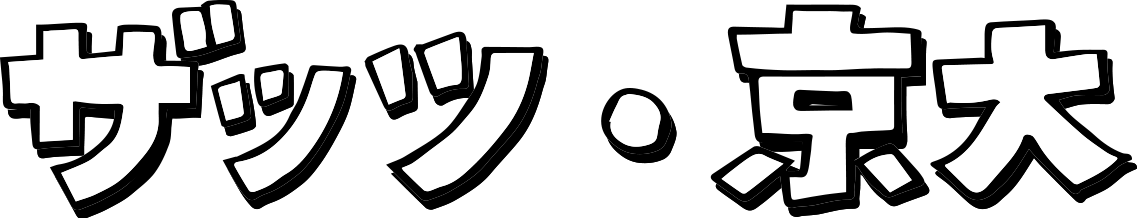
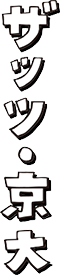
昨今のヒットチャートを見てみると、VOCALOID ™(ボーカロイド)を使って曲の制作・リリースを行う「ボカロP(ボーカロイド・プロデューサー)」の活躍も目立ちます!
自分が歌を歌わなくても曲が作れる、そして、その曲を全世界に発信できる時代。そのムーブメントの背景には、ボーカロイドという歌声合成技術の存在が。音楽シーンに革命的な影響を与えたボーカロイドですが、その開発者はなんと本学の卒業生なんです!
ボーカロイドの誕生から約20年が経ち、今年1月にはその代表的なアイコンともいえる「初音ミク」の映画が全国で公開されるなど、ますます「ボカロ」が日常に広がる中、 今回は「ボカロの父」と呼ばれるヤマハ株式会社の剣持秀紀さんにインタビュー。ボーカロイドの開発やこれからの歌声合成技術、そして剣持さんの学生時代についても迫ります。

VOCALOID (ボーカロイド)とは…
ヤマハ株式会社が開発した歌声合成技術とその応用ソフトウェア製品の総称(略称「ボカロ」)。

――本日はよろしくお願いします! まずは、剣持さんがヤマハ株式会社に就職したきっかけを教えてください。
「小さい頃からの夢だった電気メーカーで、音楽に関連する仕事ができればいいなと思っていて。しかもヤマハの本社が地元・静岡にあったので、他は考えていませんでした」
――まさに剣持さんにぴったりの就職先だったわけですね。のちに、ヤマハで、ボーカロイドが誕生するわけですが、入社してからどんな仕事をされていたのでしょうか。
「入社してから2年半は、アクティブノイズコントロールという、騒音と逆の形の音の波長を出すことで騒音をキャンセルする技術の研究開発を行っていました。その後、L&Hジャパンという会社に出向し、日本語テキスト音声合成や音声認識技術の仕事をしていました。音声や音声信号処理の分野に関しては素人だったのですが、面白そうだと思って取り組むことにしました。そして、復職後にヤマハ社内で立ち上がった歌声合成の開発プロジェクトに参加することになったのです」
――プロジェクトが発足した当時から、社内では歌声合成に対する関心は高かったのですか?
「そうですね。コンピュータ上では、楽器の音やピアノ、弦楽器の音を再現できるようになってきていたので、次は歌の出番だろう、という感覚はありました。実はそれ以前にも、歌声を合成するハードウェアを販売していたのですが、そこまでクオリティが高いものではなくて……あまり普及していませんでした。それでも、将来的には音楽制作の大部分がコンピュータでできる時代が来るだろうと考えられていましたね。楽器メーカー・ヤマハとして、ハイクオリティの製品を世の中に出す、という使命感があったと思います」


――開発がスタートして、ボーカロイドが爆発的に売れ始めるまで、7年近くかかったかと思います。それまで研究開発を継続することができたのは、なぜですか?
「開発を続けていけたのは、やはり歌声合成技術に自分が信じられる魅力があったから、そして何より面白かったからだと思います。最初は、ほんの1フレーズを合成するだけでも『何分何秒からこの音の高さで、この歌声の断片を使い、その後に音が変わる』といった要素をタイミング含めて全て紙の上で手動で計算しながらプログラムに書き込んで、開発を進めていたんです。しばらくして入力インタフェースのプロトタイプもできて、歌詞と音符を入力して合成できるようになりました。その上で、歌声の質をどうやって良くするかを試行錯誤していました。
で、やっぱり、歌が出てくると楽しいんですよね(笑)。開発に携わっている際、当時の役員が『歌は下品だから面白いんだよね』と言っていました。この『下品』という言葉には、楽器と比べて、歌というものは何となく人間の心に直接訴えかけてくる力があって、楽器とはまた違った魅力があるのかな、という意味が込められていると思います。
歌の質を上げながら、歌詞と音符を入力できる仕組みを構築できれば、クオリティの高いソフトになるという確信がありました。とにかく、やればやるほど結果が出てくるので、とても楽しかったですね」
――最初は紙の上で手動で歌声合成技術の開発を進めていたとのことですが、やはりそういった地道な開発の積み重ねがあったからこそ、今があるのでしょうか。
「基本は『地道』にでしたね。ただ、技術が大きく進展した瞬間もありました。歌声の断片をつなぎ合わせて合成を行うのですが、歌声の伸ばす部分はそのまま使い、音が変化する部分を調整してつなぐようにしてみたのですが、どうしても不自然な感じでうまくいきませんでした」
――そこをどうやって、改善されたのですか?
「人間の耳は音の変化に敏感ですが、伸ばし音の部分はあまり意識しないんですよね。つまり、伸ばし音の部分だったら調整しても違和感が少ないのでは?ということに気づいて、そこからは一気に音質が大きく改善されました」
――なるほど、その発想の転換によって、今の音質が生まれたのですね。一方で、ボーカロイドの歴史を振り返ると、「初音ミク」というキャラクターの登場も大きな転換点だったと思います。ボーカロイドと「初音ミク」の関係とインパクトについて教えてください。
「『初音ミク』というキャラクターは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社の伊藤博之さんと、佐々木渉さんを中心に考案されました。後になって考えると、コンピュータで歌を合成する技術において本質的な部分を突いていたと思います。
つまり、コンピュータが歌うと言っても、『じゃあこれは誰の歌?』という疑問が生まれますよね。でも、『初音ミク』がいると、『この子が歌っている」と思い込むことができるんですよね。ここが大きなポイントだったと思います。
そして、キャラクターの魅力もさることながら、初音ミクの誕生は歌声合成のあり方を変えた大きな要因だと思います。ボーカロイドもバージョン2となり、特に『息の成分』を再現できるようになりました。人間の声、特に歌の場面では息の成分が重要な要素で、その部分がちゃんと再現できました。これにより、『かわいい声』を上手く表現でき、キャラクターとマッチしていると感じてもらえるようになったのではないでしょうか」

――世の中にボーカロイドを受け入れてもらうためには「初音ミク」の存在が不可欠だったということですね。
「そう考えると、とにかくタイミングが重要だったな、恵まれたなと思います。初音ミクが誕生した2007年の夏、国内ではちょうど『ニコニコ動画』などの動画サイトが普及し始めていたんです。世の中にボーカロイドの存在を知ってもらう、受け入れてもらうためには、本当に良いタイミングだったのかなと思いますね。もし初音ミクの誕生とニコニコ動画の普及が半年ずれていたら、全然違う結果になっていたかもしれません」
――ボーカロイドの発展には、すべてのピースがはまるような、そんなドラマチックな背景があったんですね。剣持さんから見て、今の最新技術やボーカロイドについてどう思われますか?
「正直、ちょっと聴いただけではもう人と区別がつかないですね(笑)。ヘッドホンや、スタジオの環境でスピーカーで聞いた時に、『あ、これ合成かな?』と感じるレベルまで人間の声に近づいてきていると思います。それでも、まだ完全に人間の声ではなくて、おそらく、永遠に人間の声にはならないでしょう。ただ、だからこそ、ボーカロイドはその存在を保ち続けるのだと思いますし、これからも人間の声の完全再現を目指して研究開発が進んでいくことでしょう。
そして、今後もボーカロイドはどんどん進化していくと思いますが、過去のものが色あせることはありません。例えば、昔の『DX7』の音色が好きな人がいるように、実際の楽器と同じように、進化していく途中であっても、その時代ごとの音色は大切にされていくと思います。
つまり、ボーカロイドの歌声合成技術は、人間の歌声に近づける方向にも進んでいく一方で、より新しい表現を生み出すための道具へと進化していくと思います。これは、電子楽器が、新しい用途に転用されて新しい表現が生まれたけれど、それが、例えば最初はピアノなどの生の音を再現しようとしたのと同じように、ボーカロイドもそんな風に発展していくのではないかと思います。そして、私はその進化を願っています」

――なるほど、ボーカロイドには「楽器」としての魅力が、今までも、そしてこれからもあるのですね。剣持さん自身の今後についても教えてください。
「自分のやっていることが、間接的であれ、直接的であれ、世の中に役立ってほしいという思いがずっとあります。私の場合は、自分が手掛けたものが直接世の中に出て、実際に人々に受け入れられ、それが素晴らしい作品として形になり、さらにそれを耳にすることができる。このような体験ができることが、私にとってのやりがいです。
そして、私はこれからも若い人たちがその体験をする手助けをしていきたいと思っています。定年を迎えるあと2年は技術者としての役目を果たし、次世代に技術を受け渡していきたいと思っています」
――それでは剣持さんの学生時代についても教えてください。そもそも、本学の工学部、そして電気工学科に進学した理由はなんだったのでしょうか?
「小さい頃から電気工作が好きで、回路を組み、音を出したり、ラジオを聞いたりして遊んでいたのを覚えています。そのうちコンピュータにも興味を持つようになって、将来的には電気メーカーでエンジニアとして働けたらと思っていました。京大を志望したのは中学・高校の修学旅行で訪れた際に京都の街に魅力を感じたからです。頑張って勉強すれば可能性はあるかもしれないと思ったので、挑戦してみた、という感じです」
――大学時代を振り返って、ご自身はどんな学生だったと思いますか?
「そうですね……最初は真面目な学生だったと思いますが、入部していたオーケストラに二回生の時から熱中し過ぎまして。三回生から四回生に進級する際、研究室配属に必要な単位数が足らず、留年が決定しました……。当時の指導教員に、「君、何かしてるのか?」と尋ねられて、「オーケストラをやっています」と答えると、「オーケストラか、それもよかろう」と言われました(笑)。その後、大学院に進み、院生生活とオーケストラ活動の両立はますます大変でしたが、学生の自主性が大切にされている素晴らしい環境でした」
.jpg)
――オーケストラが青春だったのですね。確かに学業との両立は大変そうですね……。
「研究生活は苦労しましたね。夜遅くまで研究室でプログラミングやデータ解析をしたりして。ただ、自由な時間帯に研究できる環境があったのは良かったですね。粘り強く考えを突き詰めたり、問題解決する思考を磨けたりしたのも、結果として今につながっていると思います」
――なるほど、大学時代の経験がボーカロイドの開発にも活かされていたのですね! それでは最後に、今後進学を目指している中高生、そして卒業生に向けて、アドバイスをお願いします。
「京大は本当に、自分のやりたいことをとことん追求できる場所でした。進学を目指している学生さんたちには、そういった環境の中で、自分の好きなことを突き詰めてほしいですね。また、卒業された方には、仕事でも趣味でも、自分の中にある京大スピリットのようなものを今後も持ち続け、活かしていってください」
ボーカロイドの開発者として、すぐに結果につながらなくても諦めず、地道な努力とボーカロイドの価値を信じ続けた剣持さん。そのルーツをたどると、京大で培った「とことんこだわり抜く」姿が見えてきました。
ありがとうございました!
