2018.09.03
学ぶ夏フェス再び!イベント満載オープンキャンパス!
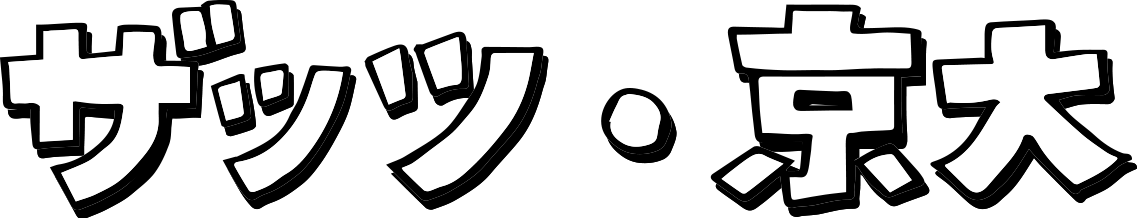
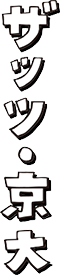
科学・技術分野において独創的な夢を持つ、意欲ある女子学生を支援する『京都大学久能賞』。その2022年度の受賞者の一人に選ばれたのが、医学部人間健康科学科 当時3回生(現4回生)の坂内佳永さんです。応募課題の一つだった「私の夢と志」というテーマのエッセイでは、「明日は私が誰かの夢 -小児がんの子供たちへ-」と題し、看護の力で子どもたちの生活に寄与したいという目標を綴られた坂内さん。そこにはどんな思いがあったのでしょうか。

――『京都大学久能賞』の受賞、おめでとうございました!まずは受賞された感想からお聞かせください。
「応募する際、過去の先輩方がどういった夢を持たれていたのかを確認したところ、素晴らしい方ばかりだったので、自分がこのなかに選ばれる自信がなくて…。面接も失敗してしまい、忘れようかと思っていたときに受賞のメールをいただき、とても驚きましたし、うれしかったです」
――面接が失敗したというのは?
「3分で話してくださいと言われていたなか、2分半にも満たず話し終えてしまったんです。『大丈夫ですか』と訊かれ、平静を装って『大丈夫です』と答えたものの、その後の質疑応答にも尾を引いてしまい(苦笑)、だめだったろうなと思いながら帰りました」
――失敗したと思っていたところでの受賞なら、なおさら驚きますよね。どういった点を評価されたと思われますか。
「これまでは『ザ・理系』という感じの宇宙医学や、工学系のハイレベルな活動をしている方が多かったのですが、私はそれとは少し違った視点での夢を持っていて、そこを評価していただけたのかなと。論文では、小児看護に携わりたいという夢に至るまでの思いや経験、海外で研究をして臨床と両立できるような看護師になりたいという目標を書き、面接でもその詳細を話したんです」
――ご自身の夢が評価されるのはうれしいですよね。
「看護師になりたいという思いは私の過去の経験から来ているものが大きく、独りよがりになっていないかと心配していました。だから外部の方に自分の夢を評価してもらい、後押ししていただいたことはとてもありがたかったです」
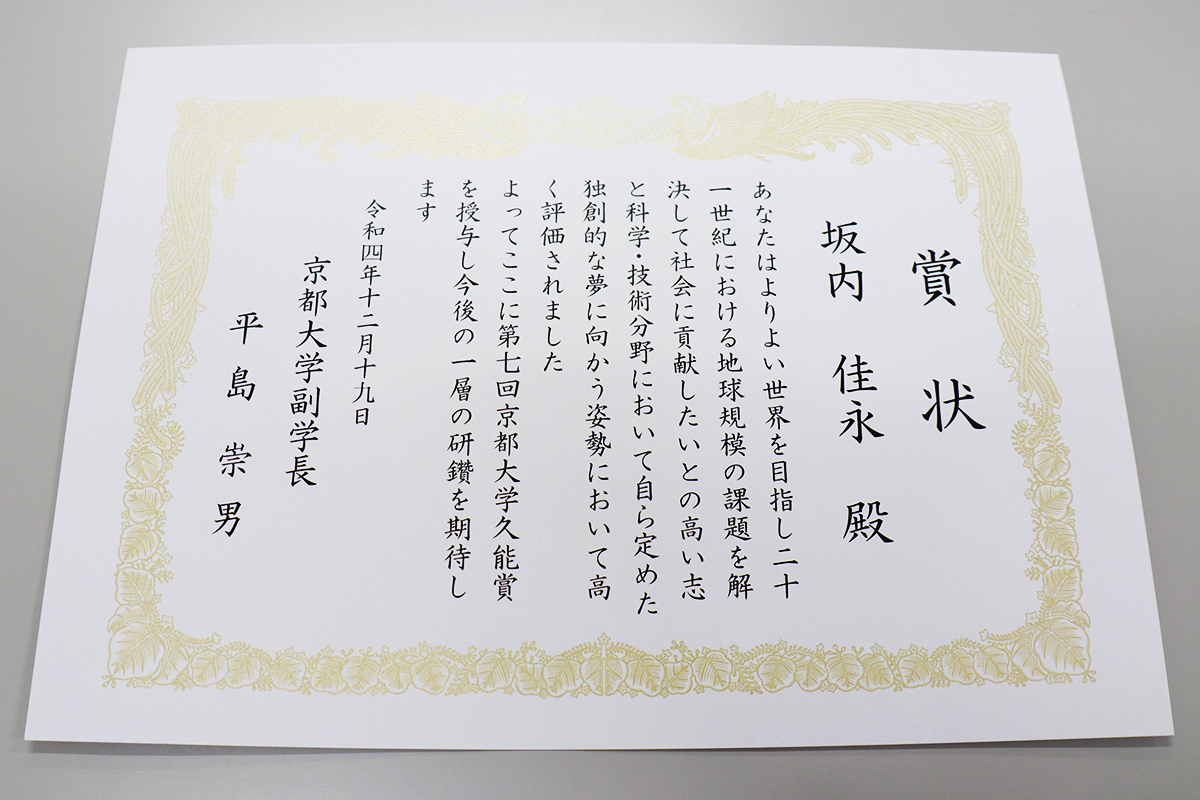
――そもそも『京都大学久能賞』に応募されたきっかけは何だったのでしょう。
「戦争などで夢を叶えられなかったからこそ今の若者の夢を応援したいという、寄附者である久能悠子様ご自身の思いに共感したことがきっかけです」
――共感、といいますと?
「私自身、テニスで強くなることが夢だったんです。もともと2歳のときに悪性リンパ腫、つまり小児がんで1年ほど入院していたのですが、その後は病気だったことを忘れるぐらい元気に過ごしていたんですよね。だけど中学1年生の冬に意識を失ってしまって…。心臓の半分ぐらいの大きさの腫瘍が見つかり、緊急手術をしたんですが、人工呼吸器をつけて寝たきりの状態が1カ月あまり続きました。その後のリハビリが本当に大変で、自分で歩けるようになるまで半年以上かかり、入院生活も約1年にわたりました」
――そんな大変なご経験をされていたんですね…。
「退院後も、今までのように走り回れないのはもちろん、勉強も遅れてしまっていたし、友達との話題にもついていけず、つらいことが多かったんです。でも、そんなときに思い出したのが入院生活だったんですよね。つらかったはずなのに、看護師さんと話した日々が自分の元気や活力になっていることに気づいたときに、看護師さんってすごくいいなと。子どもたちにとって入院が、つらいだけではなく何かを得られる経験になるような看護をしたいと考えるようになりました」
――どういうところがご自身の支えになったのでしょうか。
「長く病棟にいたので、担当の方だけでなくいろんな看護師さんが気にかけてくれていました。しゃべりに行ったら相手をしてくれたり、病室にも遊びに来てくれたり、家族のような存在で、友達もいない状況だったのでとてもありがたかったんです。実は今でも当時の看護師さんとはつながっていて、就職の相談に乗ってもらったりしています。ずっと続く関係でいられるのも、私のなかで大きな支えになっています」

――今でもつながっているなんて素敵ですね。実際に看護師を目指されるようになり、職業としての魅力はどういうところに感じられますか。
「お医者さんは多くても1日1~2回くらいしか顔を合わせませんが、看護師さんはずっと病棟にいる、身近であたたかい存在というところが一番の魅力だと思っています。どれだけ医療が発達しても、看護はその個性まで含めた患者さんそのものをみることが重要な職務です。一人ひとりに合わせて寄り添い、その人のために工夫ができるなど、柔軟なところが奥深い。そんな部分を極めたいと思うようになりました」
――確かに看護師には、医者とはまた違う役目、やりがいがあるように思います。看護師をめざすために京都大学を選ばれたのには、何か理由はあるのでしょうか。
「附属病院があり連動した研究がなされていること、しかも京都大学附属病院は各地方に1~2箇所しかない小児がん拠点病院として小児がん医療の研究にとても力を入れていることなどが大きかったです。さらに1年目に全員が一般教養を受け、看護の勉強をするのは2年の後期からなのも京大の特徴で。ほかの学校が3年かけることを1年半で学ばなければいけない大変さはあるものの、広く知見を深められるところがすごく魅力に感じています。大学に入らなくても看護資格は取れますが、患者さんと接するにも知っていることは多い方がいいと思っていて京大を志望しました」
――看護のテクニックや知識だけではないものが学べる環境というわけですね。
「しかも京大の医学部には素晴らしい先生方が集まっています。日本で初めての生体肺移植で執刀された先生もおられて、そのときのオペのビデオを見せてくださるなど、やっぱり京大に来て良かったなと感じる授業ばかりです」
――坂内さんは特色入試で入学されたんですよね。この方式を選択された理由は何だったのでしょう。
「看護師になりたいという思いが強かったため、高校でも生命・医療にかかわる研究をしていたんです。学力だけでなく、そういった経験や熱意も含めて、総合的に評価してもらえると感じ、特色入試を選びました」
――どういった研究をされていたのですか?
「私の母校には、自分が興味を持ったことを調査する『探究』という授業があったんです。そのなかで、病院の小児患者向けのプレイルームを再構築してみようと思い、現状どういうところに問題点があると患者さんたちが感じているのか、いろんなアンケートをとって、それをもとにプレイルームを新しくデザインし、3Dモデルをつくりました。
ほかにも、全国の学生が創造力を競い合う『MONO-COTO INNOVATION(モノコトイノベーション)』という大会に参加し、長期入院をする女子中高生に焦点を当てたデバイスを提案して優勝したこともあります。特許も取ったんですが、提案することがゴールだったので、商品化などの実現可能性まで考えていなかったんですよね。その経験を踏まえ、人の役に立つ研究をして、ちゃんと患者さんに届けたいと考えるようになりました」



――高校時代から活発に研究されていたんですね。2021年には「理工系学生科学技術論文コンクール」にも入賞されていますが、こちらへの挑戦のきっかけは?
「私が入学したのはコロナが蔓延した2020年で、ずっとオンライン授業が続きました。待てど暮らせど、思い描いていた学生生活が送れず、このままでは学生生活が終わってしまうと思っていたときに知ったのがこのコンクールでした。閉ざされていたオンライン生活からの解放というか、外部とのつながりをもちたいと思ったんです。そこから『小児医療における入院環境を考える』というテーマで執筆しました」
――どういったことを書かれたのですか?
「小児科には0~15歳ぐらいまでの患者さんがいるんですが、幼稚園生と中学生が求める遊び場は違いますよね。私自身も入院中、幼い子ども向けだったプレイルームに物足りなさを感じ、もっと息抜きできるような遊び場があればいいなと感じていたので、そういった改善提案をしました。それに長期入院で外に出られないのはしんどいので、季節を感じられる映像を病室に投影するなど、もっと代わり映えするような工夫があればといったことも書いています。海外の事例を見ると、お城みたいだったり、森を感じられるような場所が設けられていたりする病院もあり、面白いなと感じていて。そのあたりも海外で研究をしたいモチベーションになっています」
――海外事例などは自分で探されたんですか?
「そうですね。小児医療に関するものを調べるのが好きで、論文や文献もよく読んでいます。コンクールがあるからとかそういうわけではなく、今調べられることを今調べようと日常的にしています。やはり、やらずに後悔したくないという思いはずっとありましたので…」
――「できるときに、やるべきことをやる」というのは、やはり中学時代の…。
「そうです。今振り返ると、入院中にももっとできたことがあったなと思うんですよね。運動は無理だったにしても、もう少し勉強はできたなと思うことが今でもありますし。後悔しないよう、いろんな活動をアクティブにしていきたいと考えています」
――今も何か活動をされているんですか?
「研究ではありませんが、『Osaka Great Santa Run』という、医学部の学生を中心とした学生団体の幹部を務めています。サンタクロースの衣装を身にまとって大阪城をランニングするチャリティイベントで寄附を集め、それを資金にして病気と闘う子どもたちにプレゼントを届けたり、クリスマス会を開催したり。企業の方々や著名人にも協力してもらい、少しでも小児医療に携われるように活動しています」
――坂内さんもランニングを…?
「ある程度は走れるようになったので参加しています。今はテニスサークルにも所属しているんですよ。退院後に私の状態をわかりながらも友だちが『一緒にやろうよ』と言ってくれたことがうれしくて、その友達には朝練にも付き合ってもらって運動も元のようにではないですができるようになっています」


――それは良かったです!最後に将来の夢……、どんな看護師になりたいかを教えてください。
「小児入院患者が、入院中であっても子どもらしく生活できるように努められる看護師になりたいです。また、小児がんの治療成績はここ数十年で伸びていて、長期生存できる小児がんサバイバーも増えています。ただ、だからこそ大人になって、仕事面や生活面で新たな問題が出てくることもあり、そこにどうアプローチしていくのかも看護の仕事だと思っています。問題が起こらないよう、入院中からサポートや情報提供ができる、そういった長期フォローアップの研究や実践にも取り組んでいきたいです」
――長期フォローアップとなるといっそう、臨床と研究の両輪が大切になってきそうですもんね。
「やはり人をみる仕事ですので、現場に立ってみないとつかめないと思うんですよね。まずは臨床で人と関わりながら、役に立つ人間になりたい。そこから問題点を探り、改善できるような研究をしていけたらと思います。自分の経験をもとにした研究成果を、病院や社会に還元できるよう頑張りたいです」
――ぜひ子どもが子どもらしくいられる看護を実現させてください。興味深いお話を、ありがとうございました!