2020.01.30
京大OBがオリンピック代表内定! 世界陸上男子20㎞競歩王者、山西利和さんインタ...
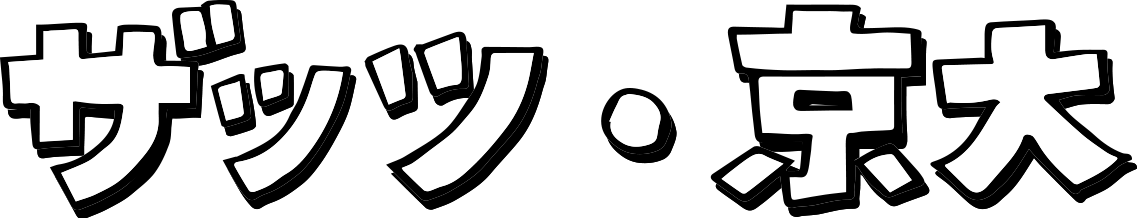

拝啓。
『ザッツ・京大』の読者の皆さま。
もう、卒業の季節ですね。
仰げば尊し、センパイの恩。
クスノキ前でも、はや幾年。
というわけで、今回の『ザッツ・京大』は、京都大学の卒業生に登場いただきます。

上田久美子さんは、京大時代は文学部(フランス語学フランス文学専修)に在籍。卒業後、製薬会社での勤務を経て、2006年に宝塚歌劇団の演出助手として入団されました。
2013年に『古事記』に材を取った『月雲の皇子 -衣通姫伝説より-』で演出家デビューを果たしてからは、観客を本質的な問いへと導く魅力ある舞台を次々に手掛け、第18回鶴屋南北戯曲賞の最終候補や、第23回読売演劇大賞・優秀演出家賞を受賞するなど、めざましい活躍を見せる上田さん。
そこで、京大生時代の「変」から、舞台にめざめたきっかけ、演出家として思う「人が才能を発揮する条件」などなど、熱くディープに語っていただきました!
——まずは学生時代について伺いたいのですが、京大時代の上田さんはどんな学生だったんでしょう?
「ジャージ姿でコケシみたいな黒髪にしていました(笑)。あ、でもちょっとおしゃれなジャージですよ。ヒールの靴は履かず、活動範囲を広げられるようにどこまでも歩いていけるサンダルを愛用していました」
——まさに劇団員というスタイルですね!
「入学当初は茶色のロングヘアーで、パステルカラーの服とか着てちゃんと大学デビューしたんですよ! でも当時の京大って、そういうことに一切興味がない、社交的じゃない変な感じの人が結構多くて。そういう自分の変わったところを認めて服装でも表現している人の方が、魅力的だなぁって気がついたんです。じゃあ自分も堂々と自分の変さをアピールした方が効率的に気の合う人が寄ってくるなと、方向性を変えました(笑)」
——「変」というのは上田さんの中で伸ばすべき個性だったんですね。
「母から『あなたをずっと育てていて、何かに集中したら他のことがどうでもよくなる変な子だと思っていたけど、そういう歪な部分がないと京大の入試問題は解けへんのかなぁ』って言われたことがあります(笑)。でも京大に入ってみたら、私ぐらいの変レベルではまったく変ではなく、もっとサラブレッド的な変人がたくさんいたんです。その人たちと比べると、私はもはや馬でもない、ドン・キホーテが乗っていた貧相な駄馬ロシナンテか、ロバみたいなものだとショックをうけました」
——そこで自分も、変人のサラブレッドをめざしちゃおうと?
「最初は『いやいや私はそうならないぞ』っていうのがあったんですが。大体みんな思うんですよね、いかにも京大的な変人になったら、恋人とかもできないからなるべく普通でいようって。でもそれだとダメだと思ったんですよ。だって普通になるということは、平均になるってこと。それって世の中にあふれる量産型のものになるってことじゃないですか。それじゃ価値なんてないじゃないですか。価値がつくのは、数が少なくて何かしら魅力を含んでいるもの。なら、わざわざ労力をかけて平均的になる、たくさんある画一的なものになるのは無駄でしかないと思ったんです」

京都大学の文学部周辺の風景。上田さんもこんなところで学んでいたのだろうか……。
——京大卒業後、製薬会社に2年お勤めになってから宝塚に入団されていますね。演出家デビューされてからは受賞も含め、周りの評価が非常に高い上田さんですが、演出する上でのこだわりはありますか?
「その時々で無意識にはあるのかもしれませんが、特にないというのが正直なところです。宝塚は『この組で、このスターで、この劇場でやるんで書いてください』っていうオーダーがあるんですね。その上で、お客さんをいかにして喜ばせることができるのか、というのは考えます。でも自分で何かをやりたい、何かを表現したいっていう視点ではあまり考えないんです」
——でも上田さんは当て書きの脚本は書かないと聞いたのですが?
「出演者を念頭に衣装から性格からすべて考えるという当て書きはしません。でもある意味、当て書きですよ? 私の場合は『こういう時代でこういう人物がいる話』っていういくつかの、物語のタネみたいなものがストックしてあって、その中で『このスターさんとこのスターさんだったらこの話が合うな』っていうのをはめる感じですね」
——やりがいやおもしろさを感じるのはどんなときですか?
「宝塚は大衆的な演劇なので、そこまでアーティスティックなことをしているつもりはありません。でも結局は自分がどこかに表現されていて、それを誰かが共有してくれている、私の話を聞いてくれているというところに癒されているのかな。もしくは、思いついたアイデアを形にするときのドーパミンがでる楽しさ、ですかね。
演出も、私自身がおもしろいと感じることを入れるわけじゃないですか。自分が観客席にいて、『次にこうきたらおもしろい』ってワクワクする内容を脳内で上演するわけですよ。私は奈良の山の麓にある農村地帯で育ったのですが、周りに同世代の友達が少なく、自然の中で一人遊びしたり本を読んだりして過ごすことが多かったんです。そんな幼少期に『もし私がこうで、こんな人がきて、こんな出来事が起こったらおもしろい』と想像力を駆使していたことを、宝塚でもしているだけなんです」
——舞台や演劇に縁がない子供時代を過ごしたことが、逆に自由な演出を発想することにつながったんですね。
「宝塚のキャストでも、地方出身の人のほうが大胆な場合があると感じています。もともと都会に住んでいて、一流のものを見て育ったというタイプの人も、それはそれですごいアーティストになる方もいます。でも、演出家の要求に素直に肯き、とんでもないことでもやってのけてしまうのはどちらかというと地方出身の方かも。そうすると舞台で輝いて見える。『こんなことをしたら変じゃない?』という常識にとらわれずに演技できるからなんでしょうかね。突出した才能を持つスターの中には、そうしたターザン的な方々も多いんです。
少し話が逸れるかもしれませんが、都市に集住してみんなが非肉体的な仕事をすることが、クリエイティブな人材が出る国を作ることにはならないんじゃないかなと、私は思っています。人が地方にバラバラに住んでいる方が、いろんな人材が生まれ、結果としていい人材がよりたくさん生まれると思うんですね。もっとみんな、地方に住むべきなんですよ(笑)」

——上田さんは、人が才能を発揮する条件とは何だと思いますか?
「人の才能とは何か、才能を発揮する条件とは何なのか、宝塚にいると日々考えてしまいます。思うに、舞台人であっても、演出や書く側にしても、そのことが本当に好きで、かつ能力が合致した人はものすごく一流になるんですね。私の場合は器用貧乏なので、いつか『このことがすごく好きだ』ってことと能力とが一致するときがくるといいなって、すごく思います。広く浅くのタイプで、芝居馬鹿と呼ばれるようなのめり込み方ができないのがコンプレックスなんです」
——お話のはしばしから舞台への愛が感じられる上田さんも、十分に芝居馬鹿といっていいと思うのですが(笑)。上田さんが魅力を感じるのは、どんな俳優や演出家さんなんでしょう?
「例えば、戦前・戦後を通じて日本映画界で活躍した高峰秀子さんは貧しい環境で育ち、『女優なんて人に身を晒すような恥ずかしい仕事についてしまった。早く辞めたい』と思いながら、生きていくために女優をやっていました。原節子さんなどもそれに近くて、そういう人たちってすごく芝居が上手だと思います。子どもの頃から人生の酸いも甘いも知ってるし、また見られて気持ちいいという快感がないから、芝居に嫌味がないんです。あれ? でもこれって、才能を発揮する条件のはずの『好き』とは対極かな?」
——昨年演出された星組公演『霧深きエルベのほとり』の原作者である菊田一夫さんも、戦前生まれで相当苦労された方ですよね。
(注)『霧深きエルベのほとり』は日本を代表する劇作家・菊田一夫が宝塚歌劇のために書き下ろした作品。初演は1963年。2019年、この作品に惚れ込んだ上田さんが新たな潤色・演出で上演した
「そうですね、菊田先生も小学校中退です。生まれてすぐ養子に出されて、台湾で転々と養育先をたらい回しにされています。『がしんたれ』という自伝がありますが、これ、本当におもしろいのでお読みになってください。事実は小説より奇なりで、こんな人生があるんだと驚かされます」

「百周年時計台記念館」を背景に、記念の一枚
——上田さんは観客を本質的な問いへと導く物語を描く方ですが、今の時代はどちらかというとライトな物語が増えているように感じます。
「今、演劇だけでなく小説でもアニメでも、ストーリーが弱くなってますよね。日常系とかいうみたいですが、『それおもしろいの?』っていうものがすごく人気があったりします。業界のいろんな人と話していても『今は現場に書ける人がいない』ってよく耳にします。たぶんそれは私も含めてですが、感情が動く体験を、みんなあまりしなくなったからではないかと思うんです。快適で感情の揺さぶられない暮らしを望む人や、そうした生き方が合う人が多いのはわかります。ただ、今の世の中は無菌化されすぎて怖いと感じるときがあります」
——社会に存在してしまっている「理不尽なもの」を見せずに、クリーンに保とうとする傾向はありますよね。
「そうですね。だから現代は、ある意味、『幸せ』な世界なのだと思います。ただ、書くことや表現することにおいては、人はいろんな理不尽や怒りを感じる気持ちの振れ幅がたくさんあればこそ、書きたいことがたくさん出てきます。私自身もここ数年は、すごく辛いとか悲しい思いをしたかというと、そうでもありません。そのせいで、自分自身にも書く力がわき起こりにくくなっているのを感じます」
——上田さんでも、そうなんですか……。
「あと、今の時代はネットやSNSで見る散文的な情報で、みんなお腹がいっぱいになっているんでしょうね。人間って食事のカロリーみたいに、1日に求める情報の摂取量がある程度決まっていると私は思っていて。常に手軽な情報に触れていることで頭がジャンクな情報で満腹になってしまい、物語に没入する時間も、何かを書く欲求も少なくなっているのではないでしょうか」
——これからの時代に必要な物語、または物語が果たす役割とはなんなのでしょう?
「人は物語に癒されます。でもハッピーエンドだけに癒されるわけではないんです。人は自分が本当に大変なときは、もっと大変なことを書いたものに癒されます。
ちなみに私が最近癒されたのは、田宮二郎さんが演じた1979年TVドラマ版『白い巨塔』でした(笑)。あのドラマって、人間の醜いところとかがちゃんと描かれてるじゃないですか。それを見ると、心の中でゴチャゴチャになってる積み木がテトリスのように整理されるというか、白黒つけなくても良い状態でスーッと収納される。それは世の中の不条理とか割り切れない感情をちゃんと描いてあるからであって、物語を通じて、自分の中にたまっていた現実への鬱屈が不思議と整理される。そういうものこそ本当は必要なのに、なかなか生み出せないなぁって思います」

——-最後に、あらためて「これが京大だ!」というのを語っていただけますか?
「私の学生時代は、周りの目を気にしない変人たちのサラブレッドが、講義やゼミとは関係なく集い、キャンパスのあちこちで演劇や哲学談義を繰り広げていました。それがおもしろくて、勉強そっちのけでよく耳を傾けていたものです。京大はそうした学生それぞれの自由が、日本のどこよりも許される場所だと思うし、これからもそういう自負を持ち続けて欲しい。
今の世の中はどんどん人間が均質化しているので、京大生ぐらいはラディカルに本質を見抜き、どれだけ変なことをしてやろうかって気概を持ち続けて欲しいですね。周囲や社会や常識が決める成功が、本当に自分にとっての成功なのかを、最大限考えられる場所が京大なのだと思います」
